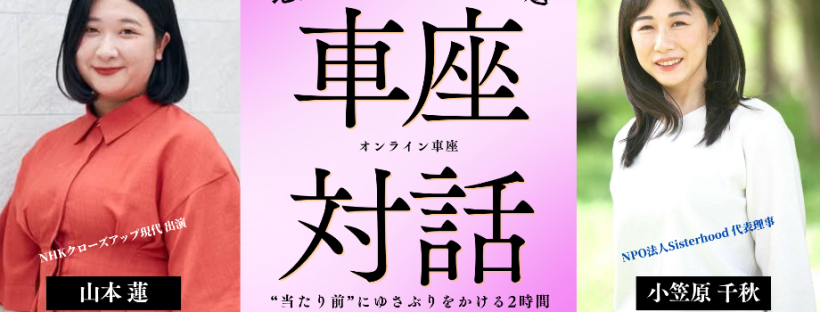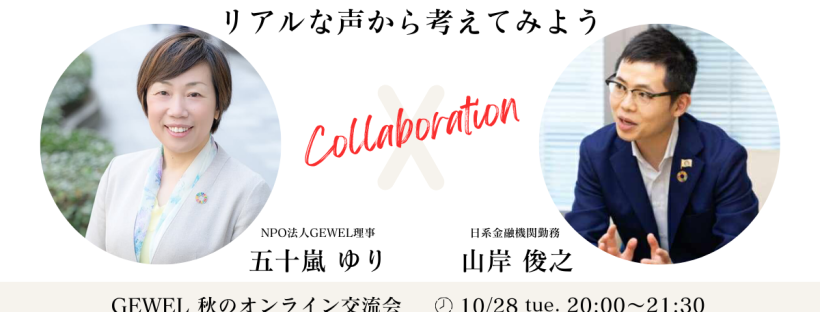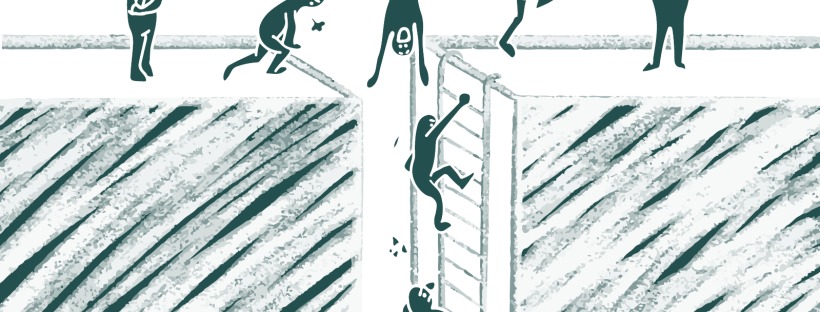GEWEL OPEN FORUM 2025
テーマ:地方 × ジェンダー課題
日時:2025年11月30日(日) 14:00-16:00(オンライン開催)
意図としては、地方におけるジェンダー課題の現状を共有し、全国の参加者同士が互いの視点・経験・課題意識を持ち寄りながら、地域課題解決に向けた対話とネットワーク形成を促進することを目的として開催しました。
全国各地(北海道・北陸・東北・中部・関西・山陰・九州)の自治体職員、民間企業会社員、中小企業経営者、市民団体、若年女性支援者など幅広い関係者が参加。
ゲストトーク
◆ 小笠原 千秋 氏(NPO法人 Sisterhood 代表理事/山形)
若年女性支援の実践と山形における“見えない構造問題”について語られました。
主な内容:
•山形県は三世代同居が全国最多、若年女性の声が家庭内で抑圧されやすい背景
•若年女性向けの既存相談窓口が機能していない現実(高齢層中心の利用)
•フリースペース「メイフラワー」では年間260名が利用
•利用者の特徴
10~20代:不登校・ひきこもり
30代:職場のハラスメント・孤立支援
•「引きこもっているのではなく、引きこも“らされて”いる構造があるのでは」との問題提起